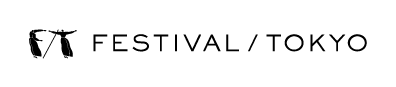- アーカイビング F/T > プログラム > メールインタビュー(森山直人)
Mail Interview
メールインタビュー
回答者:森山直人(演劇批評家)
フェスティバル/トーキョーのこれまでの取り組みについて、また今後のフェスティバルの在り方について、専門家の皆さんにメールインタビューを行いました。
――あなたが考えるフェスティバル/トーキョー(F/T)の成果と、 今後、東京のフェスティバルに期待することについて教えてください。
2009年2月にスタートしたF/Tは、「2010年代」をまさに象徴するフェスティバルだった。ネオリベ的価値観と自己責任論がもてはやされ、多くの失業者が路上の炊き出しにあふれた「年越し派遣村」や「マクドナルド難民」が社会問題化したまさにそのタイミングで、F/Tが、リミニ・プロトコルのドキュメンタリー演劇『カール・マルクス:資本、第一巻』(09春)で幕開けしたことを忘れてはならない。
2010年代の日本の現代演劇は、つかこうへいと井上ひさしを失い(10)、蜷川幸雄を失った(16)ことで記憶されるべき時代である。演劇はこの世界に、どのように応答可能なのか。喫緊のその問いに対して、F/Tは、リミニ・プロトコルやロメオ・カステルッチ、松田正隆、高山明をはじめとする「ポストドラマ演劇」を前面に押し出すことで、「演劇」を拡張する多様な「態度」と「技術」を人々に提案し、次代を担う若いアーティストや観客が、知的興奮とともにそれを受け止めたのだった。このイベントはまた、同時代のアジアに向かっても開かれてきた。ウェン・ホイ+ウー・ウェンガン『メモリー』8時間版(10)、ユン・ハンソル『ステップメモリーズ』(12)、ワン・チョン『地雷戦2.0』(13公募プログラム)などは、ここでなければ絶対に見ることができなかったはずだ。だからこそ、〈3.11〉に直面せざるをえなかったことも、思えば宿命的な事柄だった。イェリネク『光のない。』三作連続上演(12)に駆けつけたときの言いようのない緊張感は到底忘れることができない。いうまでもなく、こうしたことのすべては、初代プログラム・ディレクターである相馬千秋をはじめとする、初期スタッフ全員の歴史的な功績である。
同時にまたF/Tは、「2010年代の東京」を象徴するイベントでもあった。いうまでもなく、このイベントは、いささか時代錯誤的な「東京オリンピック招致」運動の副産物でもあった。13年に、「東京2020」開催がIOCで決定し、14年に突然のプログラム・ディレクターの交替が発表された時、何かが変質したことは否めない。その変質が何だったのかは、愚かしいだけの新国立競技場建設をめぐる茶番(15)や、コロナ禍で一年延期を余儀されたあげく、国際的イベントとは到底思えない「内向き」の論理しか打ち出せなかった五輪セレモニーの惨状(21)に、すべてが「結果」として露呈している。
したがって「東京のフェスティバル」への期待など、現段階では持ちようがない。「東京芸術祭」の宮城聰総合ディレクターをはじめとする芸術側のスタッフの力だけではどうにもならない何かが変わる必要があるからだ。ありていにいえば、それは「東京都」が変わるしかない、ということなのだが、事態が望ましい方向とは真逆に進んでいく可能性の大きさがただちに脳裏をよぎる。継承するスタッフには心からエールを送りつつも、いまは明るい未来を思い描く気分にはなれない。
――F/Tで一番印象残った取り組みと、その理由を教えてください。
10年余りの多様な活動を一言ではとても言い尽くせないが、あえてひとつに絞るなら、2009-2013年にかけてなされたフェスティバル本の刊行。無闇に紙媒体にこだわる必要はないが、あの時点で、あれだけのボリュームの「活字」を世に送り出したことは特筆すべき出来事だった。
――F/Tの中で予想外の成果・発見はありましたか? あった場合、それはどのようなものですか?
高山明/PortBの諸作品で発見した「東京」の風景。働く視点を脇に置き、歩く視点から、「東京の多様性」と出会う、という、これまでF/Tが提供してきた諸作品の、文字通りのさきがけとなった。
1968年生まれ。演劇批評家。京都芸術大学(旧名称・京都造形芸術大学)舞台芸術学科教授、同大学舞台芸術研究センター主任研究員、機関誌『舞台芸術』編集委員のほか、早稲田大学、同志社大学、立命館大学で非常勤講師をつとめてきた(2022年1月現在)。著書に『舞台芸術の魅力』(共著、放送大学教育振興会)等。主な論文に、「「演劇的」への転回――「舞台演劇」の時代の「批評」に向けて」(『舞台芸術』23号)、「「日本現代演劇史」という「実験」――批評的素描の試み」(『舞台芸術』22号)、「〈オープン・ラボラトリー〉構想へ:「2020年以後」をめぐるひとつの試論」(『舞台芸術』20号)、他多数。
森山 直人(もりやま なおと)