【F/T BOOKS】主催アーティスト選書(3)宮沢章夫
F/T11主催作品への参加アーティストの選書を紹介.
(2)は、宮沢章夫(遊園地再生事業団)。
書き下ろし選書コメントは、必読です!!
画像をクリックすると、amazon.co.jpへリンクします。
何度か小説の一部を自分の戯曲に引用したことがある。あるいは、カフカその人をモデルにした「K」という登場人物も書いたこともある。もちろん短編にはカフカの豊かな発想を読むことができるが、長編を読むときの、得体の知れない、そして静かな恐怖に浸るのもとても心地いい体験であり、そうした世界を構築する手つきそのものがとても魅力的だ。どこかで影響を受けている。なにか書こうとすると、カフカの世界観が、なんらかの姿をしてにじみ出るのを感じる。
この本に取り上げられた、「シナの百科事典」は、フーコーが『言葉と物』のなかで引用している。ボルヘスのこうした書物を読むたび、その膨大な読書量に驚かされる。そして、作品の性格を見事に取り出し提示する手つきが鮮やかだ。たとえばそれは「カフカの先駆者たち」というように分類され、読書の量だけではなく、読みの適確さになって展開される。そしてボルヘスに導かれ、ここで紹介された小説を読み、読書の世界はより広がる。だから、それをきっかけに戯曲や小説を書くことをはじめたと感じる。物語るよろこびを教えてもらったからだ。
その短編のひとつ「ロンジュモーの囚人たち」を、「旅に出られない人たちの話」として、新作『トータル・リビング 1986-2011』で使った。ほんとうにそれらは薄気味悪い話だ。読んでいるうちにさまざまな物語を喚起してくれるようで、つきないお話の種がここに仕込まれている。刺激され、影響され、同じような世界を物語として構築したい欲望をいだく。いや、しかしよく読めば、これらはフィクションではなく、どれもが事実のようにも感じ、あたかも、リアリズム小説なのかとさえ思えてくる。それというのも、それが、現実としてあってもおかしくはない、まさに「薄気味悪い話」だからだ。
おそらく、魅了されるのは、その複雑な世界の造形ではないだろうか。どことどこが繋がっているのか、なにとなにが関係しているのか、めまいのようなものを感じつつ、けれど、それはとても心地いい。『競売ナンバー49の叫び』では、邦訳に付された注釈と解説がおもしろくて、それだけ読んでも堪能したが、なにより、ピンチョンという作家の存在に興味をひかれたのは大きい。謎の作家である。めったにその姿を明らかにしない。それで、『V.』を読み、『重力の虹』で苦しんだ。新しい文学の世界を切り開いてくれる作品たちだ。
もちろんドラッグを勧めるわけではないが、ディックの視点が生み出す、ねじれた空間を、どのように演出したら舞台に出現させることができるだろう。『高い城の男』は見事な状況設定だ。易経の哲学が支配する作品全体には──もちろんエンターテインメントとしてすぐれているが──どこかドラッグの匂いを感じる。小説世界を支配する狂った空気の匂いこそディックだ。職人的に書かれた初期の作品群と、『ヴァリス』を初めとする、後期作品のテイストのちがいはどちらも捨てがたく、その中間ともいうべき位置にある『高い城の男』は、そうした対極にあるディックの傾向がバランスよく配置されている。その奇妙にねじれた空間を舞台に反映させたいのだ。
エロチックな話だった。全体を性的なものが基調として流れつつ、しかし、きわめて野心的で実験性に充ちた小説だ。このおもしろさはなにごとかと思った。さまざまなエピソードのひとつひとつから、ひどく過剰な筆致で描かれ強烈な印象を与えられる。なかでも、妊娠する女たちの姿に、母性の力の大きさのようなもの、それは大江健三郎が書く、巨大化する女のようにすべてを包み込む〈女性性〉に特有の、隠された〈権力〉に思え、その神話的な姿が魅力的だと感じた。女たちは、女から生まれる。そして、生まれた女もまた、新たな生命を宿すことで、やはり巨大化する。実験的な小説だ。過剰な物語が綴られ、エロチックな出来事の連なりによって話は進行する。なんというおもしろさだ。
漱石は『夢十夜』の各短編の冒頭に「こんな夢を見た」という言葉を書いた。つまり百閒の小説たちは、「こんな夢を見た」という言葉を小説の冒頭に書かないことによって、読む者に目眩を与える言葉の力に充ちた小説群だ。たとえば、「豹」という短い小説がある。詳しく書くのはこれから読む人のために避けるが、このわけのわからなさ、幻想性やぐにゃりと歪む小説内の光景は、読む者を奇妙な感覚にさせる。けれど、素直に笑っていいと私は考える。なぜなら、この奇妙な恐怖小説は、怖いからこそ、怖ければ怖いほど笑えるからだ。
これは、「特別な人」によって書かれたとしか言いようがない文学だ。その特別性は、江藤淳が文庫の解説に書いたように、言葉のあいだから聞こえてくる声によって、なにかがからだに響いてくることを意味するだろう。だから繰り返し読んでも、オリュウノオバの声、路地について語られる声が響き、声の美しさに惹かれ、なにも小説とは、あらすじを読むことではないのだと、あらためて教えられる。その声はとても演劇的だ。声は多くのことを教えてくれる。
たとえば、『日本近代文学の起源』における「風景の発見」によってはじめて、それは最初からあったものではないこと、発見されて初めて、「風景」が存在したことを知る。そうした「創造する批評性」ともいうべきシャープな論述が柄谷行人という思想家を特別にしている。だからいつでも読者は新鮮な気持ちでその論考に接する。新しい発見を求めて。『トランスクリティーク――カントとマルクス』における創造性もやはり同様だ。カントとマルクスという二人の思想家を交差させながら、またべつの思考を組み立てるとき、世界は新しい姿をして読者の前に現れる。私は、マルクスを、その可能性の発展として、カントの側から読むことに惹かれた。だが、それもまた、柄谷行人という人の明晰な論理と、そしてもっとも読むに価する「創造する批評性」がきわめて魅力的だったからにちがいない。
近代をどのように批判的に捉えるか。今村仁司さんから多くの考え方を得た。そのことから自分の創作を組み立て直したといっていいし、以後、なにをするにしても、近代的な生産主義から逃れることが出発点になった。たとえば、よく例に出すのは、あるワークショップの経験だ。フィールドワークに出発するにあたってA班はあらかじめ準備を念入りにしとても計画的だった。一方、B班はなにも考えずに出発した。このときA班は目的地があらかじめあってきわめて合理的だったが、しかし、フィールドワークから得た成果は低かった。なぜなら、最初から目的地があるせいで、その途中がなにも見えず、発見に乏しかったからだ。B班のいいかげんさがおもしろかった。だから成果もあった。A班にあったのは「作る精神」だ。生産主義の現場でそれはきっと合理として正しいとされる。ほんとうにそうだろうか。それに抗いたいのだ。せめて創作の場においては否定したいのだ。
穏やかな語り口だが、これはきわめて強度なメッセージだ。佐々木中さんは本書で繰り返し「革命」について語る。それは、一二世紀の「中世解釈者革命」や、マルティン・ルターを中心にしてなされた一六世紀の「大革命(=宗教改革)」への言及だが、ある時代以降の「革命」の概念が「暴力」という側面に焦点があてられるのを拒み、異なる視点で──それは「読む」という態度の言明だ──一貫して佐々木さんは、「彼らは読んだ。読んでしまった以上、読み変えなくてはなりません。読み変えた以上、書き変えなくてはならない。(中略)それが、それだけが『革命の本体』です」と、それと似た言葉を最後まで何度も繰り返す。いつからか「革命」という言葉から美しさが欠けてしまったと私には思えてならなかった。感情が震えるような力はもう存在しない。けれど文献を読み解く徹底した営為のなかから「革命」をまた新しい言葉として読者の前に再提示する。だから勇気づけられる。その言葉を口にすることで、次の〈こと〉や、次の〈時代〉を予感させる。だから、「革命」のための「戦い」は、読み、書き変えることであると同時に、その拠り所となる「文字」と「文学」の力をあらためて確認することになる。「文字こそが人類が開発した驚くべき機械である、夜の機械であり、革命の機械である」。穏やかな語り口で佐々木中はこの時代へ戦いを挑む。
もちろん、ギリシア悲劇だったら、まずは『オイディプス王』をあげるべきだろう。けれど、アンティゴネーという女性の苦悩のなかにさまざまな問題系が潜んでいるからこそ、多くの者が──たとえばそれはヘーゲルであり、近年ではジュディス・バトラー(『アンティゴネーの主張―問い直される親族関係』)だ──それに惹かれ、その物語から論考をはじめる。テキストの構造が論じるのにふさわしいだけではない。アンティゴネーという女性がもつ、強さと脆さが魅力的なのにちがいない。そうした特別な女性像は、『アンティゴネー』という作品の本質とはべつに、長い演劇の歴史のなかで、ずっと人を魅了し続けたように感じる。たとえ、男しか舞台に上がることが許されなかった時代でも(現在でも歌舞伎をはじめ、そうした演劇は数多くある)、特別な魅力を持った「女性像」がある。演劇はそうした魅力的な女を数多く生み出した。それもまた演劇の力のひとつにちがいない。
ここにある世界はまるで現在のようだ。そして、それがベケットの洞察した世界への眼差しになる。それを簡単に不条理という言葉で片付けていいのかわからないし、その戯曲を、劇の構造だけで語っていいのかわからない。来ることのないゴドーを待つ、ウラディミールとエストラゴンがいる世界は抽象的に読んでしまいがちだが、あたかもチェーホフを読むように血肉を備えた人として読むとき、また異なる世界が広がると考えたのはつい最近になってからだ。冒頭のト書きは「田舎道。一本の木。/夕暮れ。」というごく単純な指示で、だからこそ、より深くその世界を感じることができる。読み手の想像力に委ねられている。いま読むことで、いまを感じる。『勝負の終わり』もまったく同様だ。いま読むことで、いまを感じる。
ベケットとは異なり、この作品には、またべつの意味で現在を感じざるをえない。なにしろ、東北の凄惨な震災でいくつかの町が消えてしまったことを思い起こさずにいられないからだ。ソーントン・ワイルダーは「町」をテーマに、そこに生きる人々を丹念に追う。ごくあたりまえの生活の美しさを信念をこめて描写した。そこに人が生きている。生活がある。普通の生き方があり、ごくあたりまえの恋愛や結婚があり、生と死がある。その具体性のなかに人の生があること、それへの信頼があたたかな作品を生み出す。いま、この国で、上演すべき舞台ではないのか。
ところで、この「ハヤカワ演劇文庫」という企画が素晴らしいのは、『真田風雲録』のような作品を簡単に手に取ることができるからだ。作品名はよく知っていた。日本の現代演劇を語るとき、きまって福田善之とその作品が登場する。だが、長いあいだ、簡単に読むことができず、古書店を丹念にあたるか、図書館を探すことしかできなかった。戯曲の多くはそうだ。読めない作品もまだある。だからこそ、この企画が素晴らしい。そして、『真田風雲録』をラインナップに入れたこともまた、編者たちの判断の正しさだ。なぜならこれはいま読んでもとてもおもしろいからだ。五〇年も過去の作品だ。多少、背景にある政治状況を知っておく必要があるとはいえ、読み物としての戯曲の魅力を堪能させてくれる。
ここでは、太田さんの戯曲が「劇テクスト」とされていることに注目したい。もちろん本書は作者の死後に刊行されたことで、本人の意図がどこまで反映されていたのか第三者にはわからない。まして、過去の戯曲が単行本として発表されたとき「戯曲集」になっていたことを考えると「劇テクスト」が正しいかわからない。たが、それは正しいのだ。これまで当たり前に使われてきた「戯曲」という言葉だけでは、太田省吾の演劇は語りえない。そして、「劇テクスト」という言葉と、そのテクストを読む行為は、さまざまなイメージを読む者に与える。
一九八六年のことを戯曲に書こうとしたとき、その年のことを調べれば、すぐに思いあたるのが、当時、人気アイドルだった岡田有希子の投身自殺がある。事件について丹念に取材したなかから劇の言葉が生まれる瞬間の、その生々しさ、ドキュメンタリーのような発見の姿を山崎哲の戯曲に感じる。そしてその作家は、事件のなかから、事件を生み出した本質や核のようなものを、両の手で掴み出したかのように投げ出し、戯曲を読者の前に提示する。だが、戯曲に読むことができるのは、掴み出し、血生臭も漂う出来事の核にある塊が、とても繊細な言葉によって再構成される姿だ。その言葉だからこそ読む者は、ぞっとするような事件の──それはたとえばいびつな家族の姿だが──本質を知ることになる。
現在の若者の言葉を多用することの、その新しさを語られることが多い岡田利規の作品は、では、それをもっとも評価すべきだろうか。むしろ私には構造の組み立ての卓抜さ、劇というものを根底から疑う姿勢がとても興味深い。なにしろ、ある人物を、一人の俳優が演じるというあたりまえのことが疑われているのだ。記号化されてしまう「役」という考え方からどう逃れるか、それが新鮮な舞台の空気を生む。九〇年代の半ばに出現した「現代口語演劇」という種類の舞台が、できるだけもっともらしく、舞台の上で、リアルらしく振るまうことが求められていたとすれば、岡田利規はもっと不自然な、演劇の身体を求める。それは過去の演劇に戻ることではない。過去の身体ではない。不自然で、ゆがんだからだ、奇妙ないまどきの若者の言葉、構造のいびつさのすべてが、リアルなのだ。〈いま〉はそのようにしてしか表現できない。
寺山修司の正しい観客ではなかった私は、その魅力をなにも知らないかもしれない。けれど、なによりおもしろいのは、寺山にとって、その「演劇論」ではないかと考える。実験やワークショップ、訓練などで試みたさまざまな作業の経過が紹介され、それを通じて演劇を再考する。すぐれた演劇についての論考であり、と同時に、きわめて魅力的な演劇についての読み物だ。それはいまでも多くのことを教えてくれるし、かつてこんなでたらめなことをやっていた人がいたのをあらためて知ることができる。たいていの実験は寺山がすでに試みている。寺山ばかりではない、ほとんどのことは過去の演劇人がやってしまったことなのだ。では、新しさとはどこにあるのか。
太田省吾が演出した『水の駅』という舞台の美しさは、いったいなにによって生まれたのか。それを考えるには、たとえば、別役実が『ベケットと「いじめ」』で分析したような「ドラマツルギー」の考え方──それはとてもすぐれた論考だが──とはまた異なるものだ。それはなんだったか。ここで太田さんは、「劇には分厚い力がある」と語る。そして人は、劇的なるものを、それがあたりまえだとして受け取り、自身の「生」そのものを、劇の目で見ることになる。だから人は、「わたしの人生はなにもありませんでした」と口にしてしまうのだ。なにか劇的なことがなければ「なにもない」ことになる。太田さんの書き方を真似すれば、ここで重要なのは、「なにも」によって動かされてしまう人の意識だ。だから「なにも」を疑うことによって太田省吾の演劇は出現するといってもいい。「なにも」とは「劇的」のことだ。その時間の具体性、あるいは永遠性をどのように演劇的に表出するかを考えると、それがあの太田作品に特別な、たとえば、1メートルを何分もかけて進むような、ゆったりとした動きになる。時間を果てしなく引き延ばすことでようやく見えてくるもの、からだから滲み出す人の「生」がそこにある。『水の駅』はこの国の現代演劇が生み出した最良の作品のひとつだが、『劇の希望』によってその意味を教えられたし、太田さんの演劇観に私は強く影響を受けた。
- F/T BOOKS
- 2011年11月03日





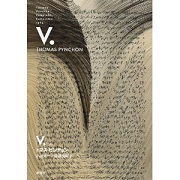




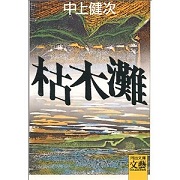






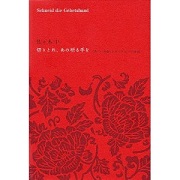




 真田風雲録(福田善之)
真田風雲録(福田善之)

